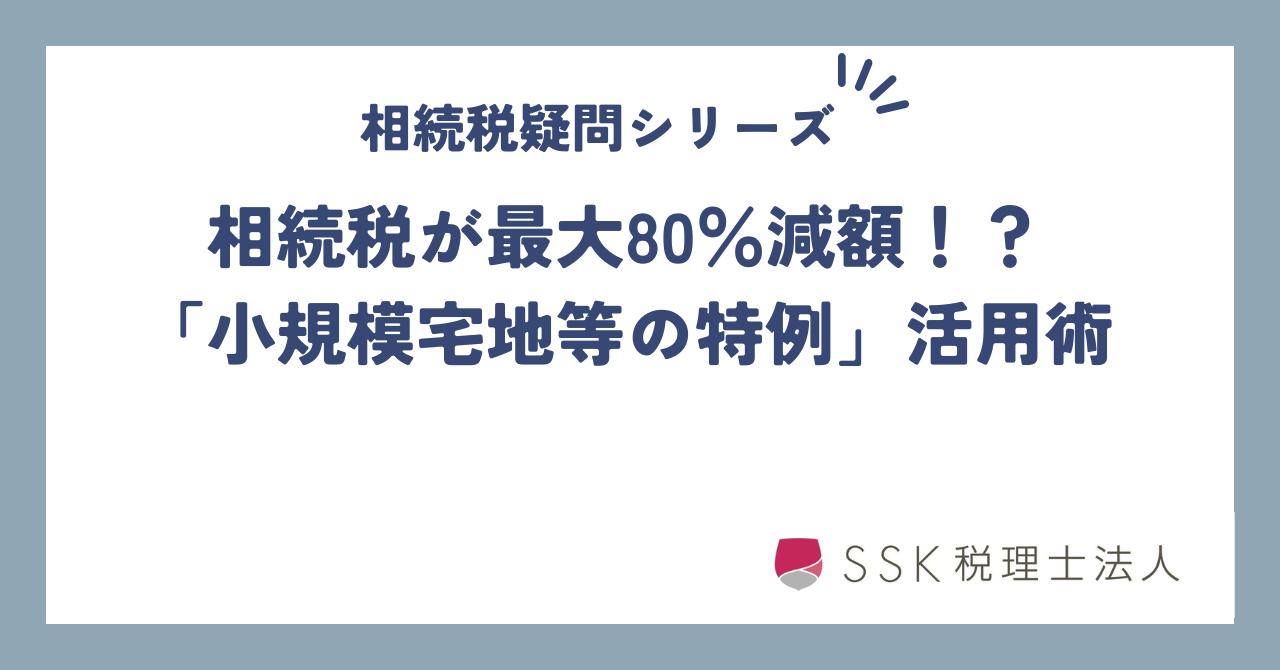相続が発生した際、多くの方にとって最も大きな財産となるのが「ご自宅」ではないでしょうか。
大切なご自宅を守り、次世代へスムーズに引き継ぎたいと考えるのは自然なことです。しかし、ご自宅の評価額によっては、相続税の負担が予想以上に大きくなるケースも少なくありません。
そんな時に知っておきたいのが「小規模宅地等の特例」です。この特例を適用できれば、
ご自宅の敷地の評価額を最大で80%も減額できる可能性があり、
相続税の負担を大幅に軽減することができます。
今回は、相続税の経験豊富な税理士である私が、この「小規模宅地等の特例」について、
特にご自宅(特定居住用宅地等)に適用する場合の要件や注意点を、具体例を交えながら詳しく解説します。
「小規模宅地等の特例」とは?
小規模宅地等の特例とは、亡くなられた方(被相続人)や生計を共にしていたご親族の事業用または居住用に使われていた宅地について、一定の要件を満たす場合に、その評価額を大幅に減額できる制度です。生活の基盤となっている土地にかかる相続税の負担を軽減し、事業や生活の継続を守ることを目的としています。
特例の対象となる宅地には、ご自宅の敷地(特定居住用宅地等)のほか、事業に使われていた土地(特定事業用宅地等)、賃貸アパートなどの敷地(貸付事業用宅地等)がありますが、今回は最も利用されるケースが多い「特定居住用宅地等」、つまりご自宅の敷地に焦点を当てて見ていきましょう。
ご自宅の敷地に特例を適用するための要件
特定居住用宅地等の特例を適用するには、「誰がその土地を取得するか」によって満たすべき要件が異なります。
1. 配偶者が取得する場合
- 配偶者がご自宅の敷地を相続する場合、特別な要件なしでこの特例を適用できます。居住継続や保有継続の要件もありません。これは、配偶者の今後の生活保障という観点から最も有利な扱いとなっています。
2. 同居していた親族が取得する場合
- 被相続人と同居していた親族(子や孫など)が取得する場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその建物に居住していること。
- 相続税の申告期限までその宅地を保有し続けていること。
3. 同居していなかった親族が取得する場合(いわゆる「家なき子特例」)
- 被相続人と同居していなかった親族が取得する場合でも、一定の厳しい要件を満たせば特例が適用できる場合があります。これがいわゆる「家なき子特例」と呼ばれるものです。主な要件は以下の通りです。
- 被相続人に配偶者がいないこと。相続開始の直前に、被相続人の居住の用に供されていた家屋に同居していた法定相続人(※)がいないこと。(※相続放棄があった場合、その放棄がなかったものとして判定します)
- 取得者自身が、相続開始前3年以内に「自己または自己の配偶者など」が所有する家屋に居住したことがないこと。(持ち家を持っていない、または持ち家に住んでいないこと)
- 相続開始時に居住している家屋を、過去に所有していたことがないこと。相続税の申告期限までその宅地等を保有していること。
具体例で見る!特例の適用可否と効果
では、どのような場合に特例が適用でき、どのくらい評価額が下がるのか、具体例を通じて見ていきましょう。(※説明を分かりやすくするため、他の財産や基礎控除等は考慮していません。)
《ケース1:配偶者が自宅敷地を取得する場合》
- 自宅敷地の状況: 相続税評価額1億円、面積300㎡
- 取得者: 被相続人の配偶者
- 【適用できるケース】
- 状況: 配偶者がこの自宅敷地を相続した。
- 解説: 配偶者が取得する場合、居住継続や保有継続などの要件はありません。 基本的に無条件で特例が適用されます。
- 効果: 特例適用後の評価額は 1億円 × (1 – 80%) = 2,000万円 となり、8,000万円の評価減が可能です。
《ケース2:同居していた親族が自宅敷地を取得する場合》
- 自宅敷地の状況: 評価額8,000万円、面積250㎡
- 取得者: 被相続人と同居していた長男
- 【適用できるケース】
- 状況: 長男がこの自宅敷地を相続し、相続税の申告期限まで引き続きこの家に住み、土地も保有し続けた。
- 解説: 「同居」「居住継続」「保有継続」の要件を満たすため、特例が適用されます。
- 効果: 特例適用後の評価額は 8,000万円 × (1 – 80%) = 1,600万円 となります。
- 【適用できないケース】
- 状況: 長男はこの自宅敷地を相続したが、相続税の申告期限前にその家を売却してしまった。(または、申告期限前に別の場所に引っ越してしまった。)
- 解説: 相続税の申告期限までの「保有継続要件」(または「居住継続要件」)を満たさないため、特例は適用できません。
- 結果: 評価額は8,000万円のままとなり、相続税負担が大きく増加します。
《ケース3:同居していなかった親族(家なき子)が自宅敷地を取得する場合》
- 自宅敷地の状況: 評価額6,000万円、面積200㎡
- 被相続人: 父(母は既に他界、父は一人暮らし)
- 相続人: 長男(持ち家あり、父とは別居)、次男(賃貸住まい、父とは別居)
- 【適用できるケース】
- 状況: 次男がこの自宅敷地を取得した。次男は相続開始前3年以内に自分や配偶者名義の家に住んだことがなく、現在も賃貸住まい。申告期限まで土地を保有する予定。
- 解説: 被相続人に配偶者や同居相続人がおらず、次男自身も持ち家がない等の「家なき子特例」の要件を満たすため、特例が適用されます。
- 効果: 特例適用後の評価額は 6,000万円 × (1 – 80%) = 1,200万円 となります。
- 【適用できないケース】
- 状況: 長男がこの自宅敷地を取得した。
- 解説: 長男は自己所有の家を持っているため、要件を満たさず特例は適用できません。
- 結果: 評価額は6,000万円のままとなります。この場合、次男が取得すれば特例を適用できた可能性があり、遺産分割の方法によって税額が大きく変わることになります。
このように、誰が取得するかによって特例の適用可否や相続税額が大きく変わる可能性があります。
知っておきたい注意点
非常にメリットの大きい特例ですが、適用にあたっては以下の点に注意が必要です。
- 適用対象面積の上限
特定居住用宅地等の場合、特例を適用できるのは330㎡(約100坪)までです。
敷地が330㎡を超える場合、超えた部分については通常の評価額となります。 - 他の特例との併用
事業用の宅地や貸付用の宅地など、他の種類の宅地にも小規模宅地等の特例を適用する場合、選択する組み合わせによって適用できる面積の上限が変わります(有利選択計算が必要)。 - 申告が必要
この特例を適用するためには、相続税額がゼロになる場合でも、申告手続きは必須です。
申告をしないと特例は適用できません。 - 遺産分割が重要
誰が自宅を取得するかで特例の適用が変わるため、遺産分割協議で慎重に話し合う必要があります。 - 二世帯住宅
建物の構造(内部で行き来できるか等)や登記状況、生計の状況によって、同居とみなされるか、または適用できる面積が変わる場合があります。 - 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
一定の要件(要介護認定を受けていた、家屋を賃貸等に利用していなかった等)を満たせば、特例を適用できる可能性があります。
まとめ:早めの相談で最適な相続対策を
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性のある、非常に重要な制度です。
しかし、その要件は細かく複雑であり、特に「家なき子特例」や二世帯住宅、老人ホーム入所などのケースでは、適用判断が難しい場合も少なくありません。
「うちは適用できるのだろうか?」「どうすれば有利に適用できる?」といった疑問や不安をお持ちの場合は、ぜひお早めに相続税に詳しい税理士にご相談ください。ご自身の状況を正確に把握し、最適な相続対策を立てることが、大切な財産を守るための第一歩となります。
私たちSSK税理士法人税理士法人では、相続税に関する初回のご相談は無料※で承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
※基本的にご相続発生後に限り、初回無料にさせていただきます。
相続対策でのご相談は、別途シミュレーションプランもございます。